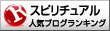夢のコントロール
戦前にほぼ途絶えてしまいましたが、かつて日本には、良い初夢を見るための”おまじない”がありました。
なぜなら、それまで数百年に渡って、初夢の内容から、その年の吉凶を占う習わしが、広く行われていたからです。
初夢が吉夢ならよいですが、凶夢だと、たった一晩の、しかも夢という”生理現象”のせいで、悪い一年を予言されたことになってしまいます。
そこで、凶夢の理不尽さを解消し、吉夢からの利益をより確実にしようと、夢の吉凶を、能動的にコントロールする方法が編み出されたのでしょう。
おまじないについて
初夢宝船
おまじないは、室町時代にはあったとされており※、江戸時代から大正時代頃までは、庶民の間でも行われていました。
「初夢宝船」と呼ばれる絵が使われますが、これには、「宝船に乗った七福神」と、「なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな(長き夜の 遠の睡(ねむり)の 皆目醒(めざ)め 波乗り船の 音の良きかな)」という和歌が描かれています

初夢宝船については、江戸時代には、正月になるとこれを売る行商人が現れたり、大正時代には、神社で初詣の参拝客に配られていたり、明治時代の金沢の新聞では、正月の風物詩として挙げられていたほど、かつては一般的だったようです。
※ 和歌の出典が、『運歩色葉集(1548年)』や『日本風土記(1592年)』と考えられるため。
具体的なやり方
おまじないは、具体的に3ステップです。
① 「初夢宝船」を用意する。
現代では入手方法が限られますが、「初夢宝船」や「初夢枕紙」などのワードで検索してみてください。
② 初夢の前の晩※※、「なかきよの~」の和歌を三回唱える。
③ 初夢宝船を、枕の下に敷いて寝る。
です。
※※ 「初夢はいつ見る夢か」の項を参照のこと。
吉夢とは
初夢における通説
初夢に見ると縁起が良いものといえば、一富士、二鷹、三茄子(なすび)。
このラインナップは有名ですが、由来については、富士は「無事」、鷹は「高い」、なすは事を「成す」という掛け言葉であるとか、徳川家康の好きなものを並べたなど、諸説あります。
なお、四以降の通常バージョンは、四扇(おうぎ)、五煙草(たばこ)、六座頭(ざとう)。
”逆夢”バージョンは、四は葬式。五は雪隠(トイレ)や糞、火事など。
(七以降は、後付けのようなので、省略します)
いくら縁起が良くても、同じ四や五なら、新年から葬式や火事の夢よりは、なるべく扇や煙草の方が……と思うのは、私だけでしょうか。
初夢以外における通説
夢の解釈は、流派によってまちまちですが、
- 恋愛運上昇 … 薔薇に関する夢、お菓子を食べる夢
- 金運上昇 … 蛇や、大便に関する夢
- 子宝に恵まれる … 鯉に関する夢
などが、典型のようです。
また、歯が抜ける夢、乗り物に乗り遅れる夢、空を飛ぶ夢などは、凶夢とみなされることが多いようです。
初夢はいつ見る夢か
一月説
新年の始まりは暦上の元日なので、本来、初夢は「大晦日の晩から元日の朝にかけて」見る夢のことでしょう。
しかし、「元日の晩から2日の朝にかけて」や「2日の晩から3日の朝にかけて」という説もあります。
その理由は、まず、室町時代以降、江戸では「大晦日~元日」説がとられていました。
一方、年越しの夜は寝ない習慣があることから、江戸中期(天明)頃からは、「元日~2日」説になりました。
さらに江戸後期になると、初商いや書初めなど、多くの新年の行事が2日に行われたため、「2日~3日」説になりました。
明治の改暦後は、「元日~2日」説が有力だそうですが、これといった正解はない模様。
本サイトのローカルルールでは、”初夢チャレンジ”は、大晦日の晩から二日の晩まで可能です。
二月説
初夢について記された、最も古い文献と言われている『山家集(平安末期)』に、
たつ春の朝(あした)よみける
年くれぬ 春来(く)べしとは 思ひ寝に まさしく見えて かなふ初夢
とあるように、もともと初夢は、たつ春=立春に見る夢でした。
また、もともと京阪神では(江戸とは違って)、初夢は節分の晩から立春の朝にかけて見る夢とされていました。
だから、もし一月に初夢を見損ねて心残りがあった場合は、二月に再チャレンジしましょう。
おまじないのすすめ
このおまじない、実は、新年の縁起かつぎにはぴったりです。
それは、どう転んでも、悪いようにはならないからです。
まず、七福神が宝船に乗っている。
縁起物 on 縁起物が、こちらに運ばれてくるかたちです。吉夢をもたらすには、十分すぎる吉祥です。
また、和歌は回文であり、上から読んでも下から読んでも同じ。凶夢を吉夢に引っくりかえす仕掛けです。
そして、凶夢を見てしまったら、夢見に使った紙を川に流せば、夢を「なかったこと」にできるのです。
ただし、現代では、紙を川に流すと(多くの自治体では)アウトです。
凶夢が気になる場合は、夢見に使った紙で少量の塩を包み、燃えるゴミの日に出す※※※とよいでしょう。
※※※ お守りやお札などを自宅で処分する方法
みなさまの2024年が、良き一年になりますよう、心よりお祈りしています(^^)
クリックしてくださると励みになります