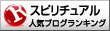重陽の節句
9月9日は、重陽の節句と呼ばれています。
陰陽五行説では奇数は陽の数とされていますが、9という数字は陽の極になることから、9が重なる9月9日は「重陽」と呼ばれます。
また、陰陽五行説に基づく暦を節句と言いますが、江戸時代、幕府が定めた式日(祝祭日や、儀式を行う日)に五節句があり、そのうちの一つが9月9日の「重陽の節句」です。
重陽の行事食
菊酒
五節句には、それぞれ行事食があり(後述)、重陽では菊にまつわるもの、特に菊酒を飲む習慣があります。
古来より、中国では菊は不老長寿のシンボルで、八百年生きたと言われる仙人・彭祖(ほうそ)が菊を薬として常用していたとか、住民がみな百歳超えの村を流れる川の源流に菊花が群生していた、などの伝説もあります。
また、後漢時代(1~3世紀)にはすでに、重陽に菊酒を飲む習慣があったそうです。
菊酒の作り方は、「菊花を、梅酒の要領で一か月ほど漬けこむ」や、「蒸した菊の花びらを器に入れ、冷酒を注いで一晩置くなど」などいろいろありますが、現在では、「冷酒を注いだ盃に、菊の花びらを散らす」という超お手軽なかたちが一般的です。
ちなみに、菊花(乾燥させたもの)は漢方でも用いられますが、こちらは頭痛やめまい、目のトラブルなどに効果があると言われており、不老長寿とは無関係のようです。(`ε´)ちぇー。
栗ご飯
菊酒以外の重陽の行事食は、栗ご飯と秋茄子です。
前者は、旧暦の9月が現在の10月にあたるため、「旬だから」という理由のようですが、後者は、「三九日(みくんち)」と呼ばれる、「旧暦9月の9日・19日・29日に茄子を食べると中風※を病まない」という言い伝えによります。
※ 発熱・発汗・咳・頭痛・肩のこり・悪寒など
なお、老舗和菓子メーカーのとらやには、「重陽」という、毎年9月7日~9日に、中部と近畿地方限定で販売される和菓子があります。

重陽らしく、栗を模したものですが、上のリンク先に価格や販売店の一覧があるので、興味ある方はチェックしてみて下さいね。
五節句の行事食
重陽以外の五節句は、人日(じんじつ:1月7日)、上巳(じょうし:3月3日)、端午(たんご:5月5日)、七夕(しちせき:7月7日)ですが、それぞれに行事食があります。
人日は七草粥、上巳は草餅やひなあられ、蛤の潮汁、端午は粽や柏餅、七夕は索餅や冷麦などですが、独自の習慣を持つ地域もあるようです。
(参考:「節句と節句料理についての一考察」
重陽に菊酒がふるまわれる神社
重陽の神事を行う神社の中には、神事の後で菊酒がふるまわれるところがあります。
例として、3社挙げておきます。
【貴船神社】
菊花神事で、巫女が舞を奉納するなどした後、最後に執り行われる直会(なおらい)で、参列者に神前から下げられた菊酒が振舞われます。また、先着30名まで神殿内で参列できます。
【上賀茂神社】
烏相撲が行われた後、境内の菊酒拝戴所でいただけます。


【車折神社】
舞楽が奉納された後、本殿前でいただけます。


実は、食用菊の旬は、重陽の節句より遅いんですよね。
食用菊生産量日本一の山形県でも、収穫は10月頃なので重陽には間に合いませんが栗ご飯のところにも書いたけど、旧暦の9月は現在の10月ですものね、刺身に添える菊を用意して、長寿を祈願しながら揚げ茄子や茄子の味噌炒めあたりで菊酒を一献、というのも、またオツなものです。
ま、私はお酒さえ飲めれば、オールオッケーですけどね(笑)
クリックしてくださると励みになります